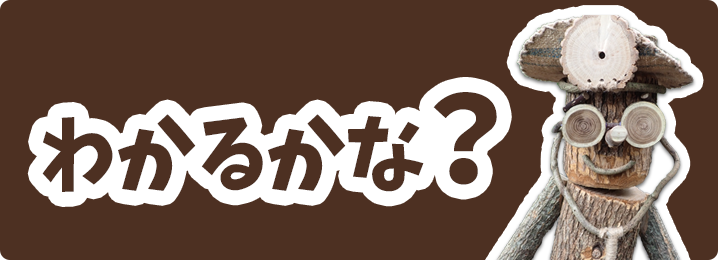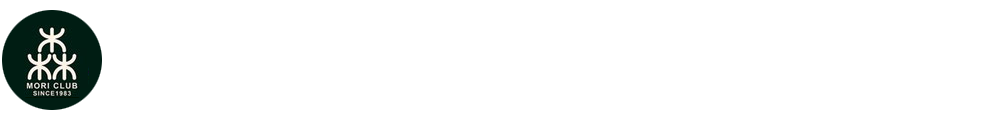5月
9~10月
ハナビツツジの花

ヒラドツツジの花

つながってるいきもの
ツツジの花に来るアゲハチョウ
花の多くは昆虫に花粉を運んでもらい、種を作ります。そのために昆虫が来るように蜜を出すわけですが、花に集まる昆虫は様々です。そこで、ある決まった昆虫に花粉運びをしてもらおうと花の作りを変えたりします。ツツジは大きく開いた花の奥に蜜があり、アゲハチョウがもぐりこむようにして吸うときに翅に花粉がつくよう長い雄しべを持っています。
カラスアゲハ成虫


クロアゲハ成虫


ジャコウアゲハ成虫

ナガサキアゲハ成虫

ナミアゲハ成虫

ミヤマカラスアゲハ成虫

オキナワルリチラシ(蛾)

キドクガ(蛾)
キドクガの成虫

キドクガの成虫

キバラケンモン(蛾)の幼虫

ツツジグンバイ
ツツジの害虫として知られ、成虫幼虫ともに葉裏で汁を吸います。吸われた葉は白くまだらになり見栄えが悪くなります。


テングイラガ(蛾)
幼虫は肉質突起上に多数の毒棘を持ち、触れると激痛を与えます。赤く腫れますがほとんど痒みはなく、3日位で治癒します。
テングイラガの成虫

テングイラガの幼虫

ルリチュウレンジ
幼虫は集団でツツジの葉を食い荒らします。枝先が坊主になったりします。成虫はツツジ付近を飛んでいることが多いです。
ルリチュウレンジの幼虫

ルリチュウレンジの成虫

エグリヅマエダシャク(蛾)

コツバメ
近年随分と減ってしまった昆虫の一つにコツバメという小さなチョウがいます。春だけその姿を見せ、小さくて地味な色をして林縁や枝先を素早く飛び回りますので、なかなか目に止まりません。こういう春にしか現れない生き物たちをスプリング・エフェメラルと呼びます。幼虫はツツジ科のアセビ、シャシャンボ、ツツジ、シャクナゲなどを食べます。
コツバメ成虫


オカモトトゲエダシャク(蛾)
クワトゲエダシャクに似ていますが、本種は中横線(黒い線)の外側に広く白い帯が出ます。メスはなかなか見つかりません。幼虫は触るとすぐに丸くなります。色的には鳥のフンにでも擬態しているようですが、いつも歩き回っているので、かえって目立ってしまっているようです。1~2週間で蛹化しますが、羽化するのは来春です。夏、冬越しが難しく、普通種の割には飼育羽化させるのが難しいガです。

コガタツバメエダシャク蛾

ゴマフキエダシャク蛾

ナカウスエダシャク(蛾)
ウスバキエダシャク、ウスバシロエダシャク、およびヒメナカウスエダシャクに似ていますが、本種は春~晩秋に出現し低地~山地にいます。前翅は全体に暗く、中央部分がメスでは白。地味なエダシャクの中で晩秋まで残っているのはこの種がほとんどです。


ニトベエダシャク(蛾)

ヒメノコメエダシャク蛾
体を斜めにして、腹部の先端を片方の翅に触るように曲げてとまることが多いです。

フトフタオビエダシャク蛾
個体の変異が多いです。ウスジロエダシャクに似ますが、本種は外横線が斜めに走ります。内外横線の曲がり具合がより強いです。

モンシロツマキリエダシャク蛾
平野まで広く分布するので見かけることが多いです。

リンゴツノエダシャク蛾

やってみよう!