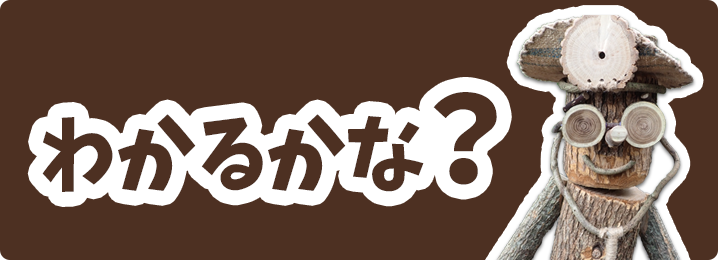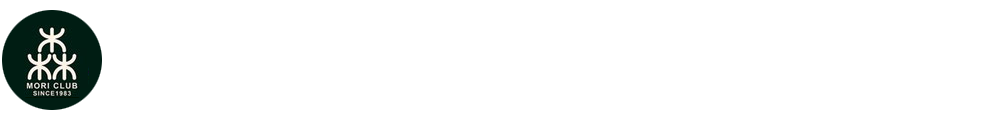6月
その年の秋





クリの紅葉

つながってるいきもの
ヤママユ
幼虫はクリ、クヌギ、シデなどを食べ、成虫は8月下旬から9月上旬にかけて現れる大型のガです。成虫は個体によって様々な色合いがあり、最もバラエティーに富んだガの一つです。山では早い木はそろそろ紅葉が始まりますが、その色を真似ているのでしょうか。これら食樹の葉には揃って縁にそって突起があり、幼虫に生える毛はそれを真似ているようです。
ヤママユのオス

ヤママユのオス

ヤママユのオス

ヤママユのオス

ヤママユのオス

ヤママユのオス

ヤママユのメス

ヤママユのメス

ヤママユのメス

ヤママユの若齢幼虫

ヤママユの終齢幼虫ようちゅう

ヤママユの終齢幼虫ようちゅう

ヤママユの蛹

ヤママユの卵

アカイラガ(蛾)
幼虫は大きな突起に、更に二次の刺を持っていますが、イラガ科の中で刺はかなり細い方です。
アカイラガの成虫

アカイラガの幼虫

アカジママドガ(蛾)
南日本では区別の付かない近縁種がいますので注意が必要です。

アカヒゲドクガ(蛾)
幼虫に毒針毛はありませんが、強い接触により軽く赤くはれ、1時間以内には治ります。

アカフヤガ(蛾)
ウスイロアカフヤガよりも色が薄いです。他種に比べ翅の中央にあるそら豆の形の紋が不明瞭で、黒い環になっているのが特徴です。

アトジロエダシャク(蛾)
春にだけ現れる蛾です。

ウスアオエダシャク(蛾)
前翅のスジが細くて鮮明です。

ウスクモエダシャク(蛾)

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

エゾヨツメ(蛾)

オオトビモンシャチホコ(蛾)

オオバナミガタエダシャク(蛾)
春の個体は夏の個体より明らかに大型。前翅裏先端に特徴的な白い紋があります。ウスバミスジエダシャクに似てはいますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では一様に黒です。裏側の前翅先端部に淡白色の紋があります。前翅真ん中の2本の線が後翅に近づいても平行です。

カギシロスジアオシャク(蛾)

カギバイラガ(蛾)

カシワマイマイ(蛾)
カシワマイマイの成虫

カシワマイマイの幼虫

キイロトラカミキリ
各種の花やコナラ・クヌギの伐採木に集まります。クリなどの花でも見られます。

キマエアオシャク(蛾)

キマダラカミキリ
外灯の灯りやクリの花によく飛来します。クヌギ・クリ・ネムノキなどの衰弱木の幹に集まります。赤褐色の下地に生える黄金色の微毛で覆われ、 光の加減で翅の模様の見え方がいろいろ変わります。

ギンシャチホコ(蛾)
幼虫はミズナラの葉に止まっていると、背中の突起が虫食いのように見えます。

クスサン蛾)

クチバスズメ(蛾)
クチバスズメの成虫

クチバスズメの蛹

クチバスズメの幼虫

クヌギカレハ(蛾)の幼虫

クリアナアキゾウムシ
幼虫はコナラやクリなどの根部を食
べます。成虫は比較的大
きな食樹の幹の低い部分で見つかります。

クリオオアブラムシ
新梢や小枝・幹の樹皮などに集団で生活しています。
クリオオアブラムシとクロオオアリ

クリオオアブラムシ

クリシギゾウムシ
シギゾウムシの仲間はみな長い口を持ち、ドングリなどの木の実に穴をあけて産卵します。中で育った幼虫は落ちた種から出てきますが、コリやクヌギから出てくる幼虫はクリ虫と呼ばれ、川釣りの餌になります。
クリシギゾウムシの成虫

クリシギゾウムシが空けたクリの実の穴

クロシタアオイラガ(蛾)

クロスジアオシャク(蛾)

クロスジキンノメイガ(蛾)

クロテンフユシャク(蛾

クロボシツツハムシ
赤と黒のなかなかきれいな成虫です。鳥などが食べないテントウムシに擬態しているようです。

クロモンアオシャク(蛾

クワゴマダラヒトリ(蛾
クワゴマダラヒトリの成虫

クワゴマダラヒトリの幼虫

コシアカスカシバ(蛾)
コシアカスカシバの成虫


コシアカスカシバの被害木

コフキサルハムシ
メリケン粉の中に落ちたのではないかと間違うほど、体に白い粉かいっぱいついています。手であまり触ると白い粉が取れて黒い地肌が出てきます。

ゴマケンモン(蛾)

ゴマダラオトシブミ


イチモンジチョウ
山地の明るい林縁を飛び回り、ウツギやクリなどの花にきます。前翅の白紋の現れ方が、近似のアサマイチモンジとの見分け方です。

ゴマダラカミキリ
生木の幹に傷をつけて産卵します。幼虫は木の内部を食べるため、ミカンなどの果樹では被害が大きいです。
ゴマダラカミキリの成虫

ゴマダラカミキリがつけた木の傷

シロスジカミキリ
日本産では横綱級の大きなカミキリムシです。捕まえると胸の部分を伸縮させてギーギーと鳴きます。昼間はアカガシやアラカシの梢にいて枝や皮をかじって食べていますが、夜になると幹まで降りてきて樹皮を噛んで傷つけ、そこに産卵します。一個産んだら少し横に動いてまた産卵を繰り返しますので、幹を横に取り巻いたような産卵痕が残ります。
シロスジカミキリ成虫

シロスジカミキリ産卵痕

シロスジカミキリ幼虫の食害

シロスジカミキリ幼虫の食痕

シロテンウスグロヨトウ(蛾)
ヒメサビスジヨトウに似ていますが、本種は前翅の外縁が丸っこくなります。メスには前翅の中横線の外側にクリーム色の点があります。

シロテンエダシャク(蛾)

シロフフユエダシャク(蛾)
2月から3月の梅の花の咲くちょっと前に出てくる種です。最近関東では1月終りから見られるようになってきたそうです。色には白っぽいものから黒っぽいものまで変異があり、メスの体色も灰色から黒まで変異があります。

タカサゴシロカミキリ
成虫はこれらの植物の葉裏にとまり、主脈をかじって食べます。夜間は伐採木や枯れ木に集まります。

ツマジロシャチホコ(蛾)

テングイラガ(蛾)
幼虫は肉質突起上に多数の毒棘を持ち、触れると激痛を与えます。赤く腫れますがほとんど痒みはなく、3日位で治癒します。
テングイラガの成虫

テングイラガの幼虫

トガリシロオビサビカミキリ
広葉樹の枯木や弱った木に集まりますが特にフジに多いです。
トガリシロオビサビカミキリの成虫

トガリシロオビサビカミキリの幼虫

トガリシロオビサビカミキリが空けた穴

トゲヒゲトラカミキリ
広葉樹の伐採木に集まるほか、カエデ・ハイノキ・クリなどの花に集まります。

トビイロカミキリ
クリなどの花に集まり、灯火にも来ます

ナカアオフトメイガ(蛾
斑紋に変異があります。前翅が真っ黒に近くて、不明瞭でも太い帯があるなら、本種の可能性が高いです。ウスグロフトメイガに似ていますが、本種の前翅外横線が後縁あたりで水平になる傾向があります。

ナシイラガ(蛾)

ナミスジコアオシャク(蛾)

ヒメツバメアオシャク(蛾)

ベーツヤサカミキリ
成虫はシイ・クリなどの花にあつまるほか、灯火にも飛来します。

ベニカミキリ
竹林で見られるほかアブラナ・クリ・ハクウンボク・カナメモチなどの花にも集まります。

ホソウスバフユシャク(蛾)
Inurois属では冬の最後の方に出現する種。冬の終わりを告げる蛾です。

ホソバトガリエダシャク(蛾
ヒロバトガリエダシャクに似ていますが、本種の前翅の方が細いです。

ホソバハラアカアオシャク(蛾
ハラアカアオシャクやウスハラアカアオシャクよりも小さいです。後翅の合わせ目のすぐ上、クリーム色のお腹に赤い飾毛があります。

マイマイガ(蛾)
幼虫の顔は(┃ω┃)。卵塊には産卵時にメスが植えた毛があります。
マイマイガの成虫

マイマイガの幼虫

マエキカギバ(蛾)

ミヤマカミキリ
夜間樹液に集まり、食樹の裂け目などに産卵します。灯火にも来ます。
ミヤマカミキリの成虫

ミヤマカミキリの被害を受けた木

ムクゲコノハ(蛾)

モモノゴマダラノメイガ(蛾)
モモノゴマダラノメイガの成虫

モモノゴマダラノメイガの幼虫

モンシロドクガ(蛾)
幼虫は極めて多数の微細な毒針毛を持っていて、蕁麻疹のような皮膚炎を起こします。痒みはとても強く治癒に約10日かかります。
モンシロドクガの成虫

モンシロドクガの幼虫

ヤマトカギバ(蛾)

ウラゴマダラシジミ
イボタ類がはえる湿地や川沿いで見られ、イボタやクリでよく吸蜜します。

やってみよう!