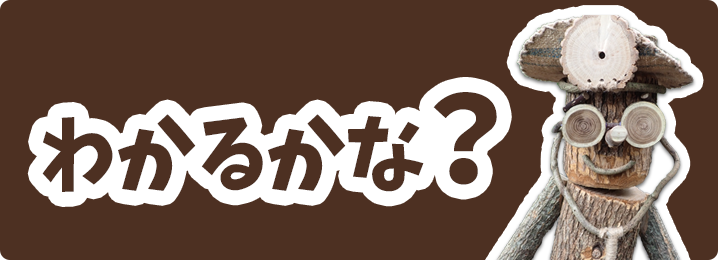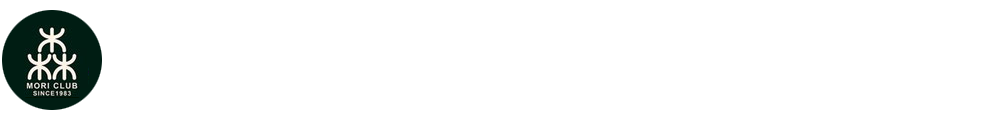5月
9~11月




鹿児島県蒲生の大楠(日本一)

つながってるいきもの
クスベニカミキリ
体は円筒形で赤く、太くて黒い触角をピンと前に揃えて飛ぶ独特の格好をしているのがクスベニカミキリです。むかしはアカメガシワの花などに来て飛び回るのが見られましたが、最近はなぜか急激にいなくなっています。食樹が減ったわけではないのです。幼虫はクスノキ、タブなどの細い枝先の内部を食べます。小指ぐらいの部分から切り落とす生態があります。
クスベニカミキリ

アオスジアゲハ
クスノキ、ヤブニッケイ、タブノキなどのクス科植物を食べる身近なチョウにアオスジアゲハがいます。黒い地に明るい青緑の斑紋を並べ、梢を敏捷に飛び回るかっこいいチョウで、子どもたちはぜひ捕まえたいと思うようです。普通だとなかなかネットの届く範囲には来ないのですが、アザミ、トベラ、ノブドウ、ソクズなどの花で待てばやってきます。
アオスジアゲハ終齢幼虫

アオスジアゲハ成虫

アオスジアゲハ蛹

ウスクモエダシャク(蛾)

オオツバメエダシャク(蛾)

クスサン蛾)

シンジュサン蛾
シンジュサンの成虫

シンジュサンの幼虫

シンジュサンの蛹

チャミノガ(蛾)

ツマジロエダシャク(蛾)

ヒロヘリアオイラガ蛾)
主に市街地や果樹園などで見られる外来種です。幼虫は軽く触っただけで刺します。かなり痛いです。幼虫はアオイラガに似ていますが、本種幼虫は、背中中央に細く暗色の縦筋があり、2齢ぐらいまでは集団行動を取ります。
ヒロヘリアオイラガの成虫

ヒロヘリアオイラガの幼虫

ベーツヤサカミキリ
山の中腹などでスダジイの花をすくうと、いろいろな昆虫が網に入るので楽しいです。ハチやハナアブとともに小型のゾウムシ、ハムシ、ハナムグリ、トラカミキリ、ハナカミキリなどとともにベーツヤサカミキリが入っているかもしれません。スマートでちょっと優しい感じの小型のカミキリで、幼虫は枯れたカゴノキの幹を食べます。少ない種類です。
ベーツヤサカミキリ成虫

ホシベニカミキリ
成虫は主にタブノキの樹木にあつまって新梢の樹皮を食べ、太枝の樹皮を楕円形にかじり取って産卵します。かじられた新梢は枯れて黒変するので、本種がいることが遠目にもわかります。

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

コガタツバメエダシャク蛾

フトフタオビエダシャク蛾
個体の変異が多いです。ウスジロエダシャクに似ますが、本種は外横線が斜めに走ります。内外横線の曲がり具合がより強いです。

モンシロツマキリエダシャク蛾
平野まで広く分布するので見かけることが多いです。

やってみよう!



佐賀とのつながり