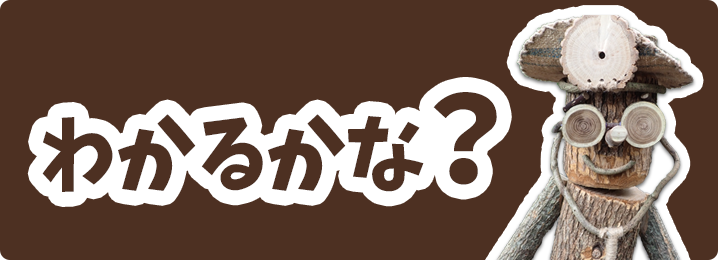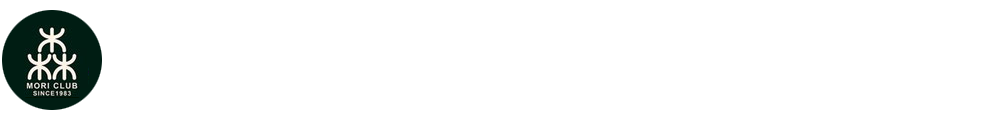4月
9月








つながってるいきもの
アミメリンガ
オニグルミだけを食べる昆虫はオナガシジミ、オニグルミノキモンカミキリなど何種かいますが、その一つがアミメリンガというきれいで可愛らしいガです。採集された昆虫のリストの中に入っていると、アミメリンガ→オニグルミ→沢がある→良い状態の自然林というふうに、実際の現地を見ないでもその場所の自然環境を想像特定することができます。
アミメリンガ成虫

アカジママドガ(蛾)
南日本では区別の付かない近縁種がいますので注意が必要です。

アジアホソバスズメ(蛾)
モンホソバスズメに似ていますが、本種は亜外縁線の湾曲が浅いです。

アトジロエダシャク(蛾)
春にだけ現れる蛾です。

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

エゾスズメ(蛾)
エゾスズメの成虫

エゾスズメの幼虫

オオコブガ(蛾)

オオミノガ(蛾)


オガサワラカギバ(蛾)

オカモトトゲエダシャク(蛾)
クワトゲエダシャクに似ていますが、本種は中横線(黒い線)の外側に広く白い帯が出ます。メスはなかなか見つかりません。幼虫は触るとすぐに丸くなります。色的には鳥のフンにでも擬態しているようですが、いつも歩き回っているので、かえって目立ってしまっているようです。1~2週間で蛹化しますが、羽化するのは来春です。夏、冬越しが難しく、普通種の割には飼育羽化させるのが難しいガです。

クスサン蛾)

クルミハムシ
クルミハムシの成虫

クルミハムシの葉の食べあと

クルミハムシの糞

クロオビリンガ(蛾

クロテンフユシャク(蛾

コフキサルハムシ
メリケン粉の中に落ちたのではないかと間違うほど、体に白い粉かいっぱいついています。手であまり触ると白い粉が取れて黒い地肌が出てきます。

コマバシロコブガ(蛾

サラサエダシャク(蛾

シロシャチホコ
本州から九州にかけて分布し、成虫は5~6月と8~9月の年2回見られます。明るく灰色っぽい、そして毛深い印象を持っています。幼虫は驚かせると、典型的なシャチホコガ科の特徴であるシャチホコ型にのけぞります。カバノキ科のアカシデ、イヌシデ、クマシデなどやブナ科、クルミ科、ニレ科、マンサク科、バラ科などかなり広範囲の植物を食べます。
シロシャチホコ成虫

シロシャチホコ終齢幼虫

タイワンイラガ(蛾)

トガリシロオビサビカミキリ
広葉樹の枯木や弱った木に集まりますが特にフジに多いです。
トガリシロオビサビカミキリの成虫

トガリシロオビサビカミキリの幼虫

トガリシロオビサビカミキリが空けた穴

トサカフトメイガ(蛾)
オスは鱗毛が前を向きます。
トサカフトメイガの成虫

トサカフトメイガの幼虫


バイバラシロシャチホコ(蛾)
シロシャチホコに似ています。シロシャチホコより黒点が少なく、鱗粉による盛り上がり?による翅のザラツキ感が少ないです。
バイバラシロシャチホコの成虫

バイバラシロシャチホコの幼虫

マルモンシロガ(蛾)

ムクゲコノハ(蛾)

ムラサキシャチホコ(蛾)
成虫はとまると丸まった枯葉に擬態しますが、翅の模様のさまがいかにも立体的に見えるからです。
ムラサキシャチホコの成虫

ムラサキシャチホコの幼虫

ヨツキボシカミキリ成虫


ヨツメエダシャク(蛾)
ヨツメエダシャクの成虫

ヨツメエダシャクの幼虫

シャチホコガ(蛾)
シャチホコガの成虫

シャチホコガの幼虫

ヒロバトガリエダシャク(蛾)
春のエダシャクの定番です。ホソバトガリエダシャクに似ていますが、本種の前翅が太く、翅が白っぽいです。また、後翅は純白です。

フトフタオビエダシャク蛾
個体の変異が多いです。ウスジロエダシャクに似ますが、本種は外横線が斜めに走ります。内外横線の曲がり具合がより強いです。

やってみよう!
オニグルミの実でつくってみよう!
熟す前は、緑色で厚い皮に包まれているオニグルミ。熟すと皮がむけてかたい殻に包まれたクルミの実が出てきます。殻はかたくて割るのは大変ですが、中には栄養たっぷりのおいしい種子が入っています。オニグルミの実をよく観察してみると、しわのような凸凹がありますが、一つ一つ違う模様をしています。個性豊かなオニグルミ、自分だけのお気に入りの形や模様を探してみてくださいね♪
\オニグルミのストラップ/

つくり方
1,オニグルミの実に電動ドリルで穴をあけて、ヒートンをつけます。
2.好きなビーズやひもをつけます。
3,オニグルミの実にニスを塗って出来上がり♪