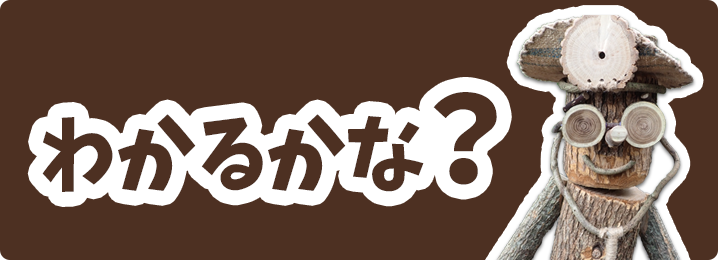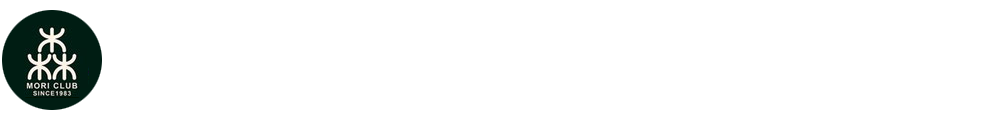5~6月
9~10月





つながってるいきもの
エゾミドリシジミ
ミズナラは佐賀県では脊振山の山頂近くにわずかに見られます。この木を食べるチョウとしてはゼフィルスと呼ばれるミドリシジミの仲間のエゾミドリシジミ、ウラミスジシジミ、ジョウザンミドリシジミがおり、いずれも少ないです。残念ながらジョウザンは九州には住んでおらず、エゾミドリやウラミスジはおもに九州中央部の高い山にしかいません。やっとできた芽に産卵するため、エゾミドリシジミのメスは7月から10月までを生き延びます。Favonius属の他のミドリシジミと同じく、オスの翅表の光沢は青みが強く、野外での同定は訓練が必要です。とくにジョウザンミドリシジミと似ていますが、本種の方が尾状突起が短く、前翅から後翅肛角にかけての白帯は同じ幅です。白帯を縁取る暗灰色帯はジョウザンに比べて濃くなります。
エゾミドリシジミ成虫

エゾミドリシジミ成虫

アオスジアオリンガ(蛾)
夏型はアカスジアオリンガに似ていますが、本種は前翅の白帯が平行で間隔が広いという違いがあります。

アオセダカシャチホコ(蛾)
名前にアオとついていますが黄緑色で、黒いバツ印が特色です。

アカシジミ
九州の低い山や丘ではアカシジミはとても珍しいチョウでした。しかし最近は所々で見かけられるようになりました。幼虫はコナラやクヌギを食べますが、炭を作るための林の伐採がなくなり、コナラが大きく育ったからではないかと思われます。5月下旬から6月にかけて成虫が発生します。午後3時から夕方にかけてコナラの樹上を活発に飛びまわります。
アカシジミ成虫




アカネシャチホコ(蛾)

アトジロエダシャク(蛾)
春にだけ現れる蛾です。

ウスアオエダシャク(蛾)
前翅のスジが細くて鮮明です。

ウスイロギンモンシャチホコ(蛾)

ウスギヌカギバ(蛾)

ウスクモエダシャク(蛾)

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

エゾカギバ(蛾)
表の横脈点てんが無く、色が暗めです。

オオトビモンシャチホコ(蛾)

オオバトガリバ(蛾)
花の蜜や花粉を食べるために各種の花に集まります。ホソトガリバに似ています。前翅の幅,後翅中央の淡色帯の幅が区別点です。

オビカレハ(蛾)
オビカレハの成虫

オビカレハの幼虫

カギシロスジアオシャク(蛾)

キリバエダシャク(蛾)

ギンシャチホコ(蛾)
幼虫はミズナラの葉に止まっていると、背中の突起が虫食いのように見えます。

クスサン蛾)

クロサンカクモンヒメハマキ(蛾)
落葉広葉樹林の林床が午後やや暗くなったころ、チラチラと飛び回ります。

クロズウスキエダシャク(蛾)

クロテンフユシャク(蛾

クロナガタマムシ
晴れた日の日中に、主にブナ科コナラ族の伐採木に集まって産卵します。

コトビモンシャチホコ(蛾)

ゴマケンモン(蛾)

シロオビフユシャク(蛾

シロスジカミキリ
日本産では横綱級の大きなカミキリムシです。捕まえると胸の部分を伸縮させてギーギーと鳴きます。昼間はアカガシやアラカシの梢にいて枝や皮をかじって食べていますが、夜になると幹まで降りてきて樹皮を噛んで傷つけ、そこに産卵します。一個産んだら少し横に動いてまた産卵を繰り返しますので、幹を横に取り巻いたような産卵痕が残ります。
シロスジカミキリ成虫

シロスジカミキリ産卵痕

シロスジカミキリ幼虫の食害

シロスジカミキリ幼虫の食痕

シロフフユエダシャク(蛾)
2月から3月の梅の花の咲くちょっと前に出てくる種です。最近関東では1月終りから見られるようになってきたそうです。色には白っぽいものから黒っぽいものまで変異があり、メスの体色も灰色から黒まで変異があります。

スズキシャチホコ(蛾)

セダカシャチホコ(蛾)
幼虫は糞を投げます。

ツマキシャチホコ(蛾)
Phalera属内での本種の特徴は、翅頂の黄白色紋の内縁が赤褐色であることです。
ツマキシャチホコの成虫

ツマキシャチホコの幼虫

ツマグロフトメイガ(蛾)

トビモンシャチホコの(蛾)幼虫

ナカキシャチホコ(蛾)
各横線が不明瞭な個体が多いです。ルリモンシャチホコに似ていますが、本種は前翅前縁基部がその下の基部より黒く、前縁中央が目立って白いです。

ナカモンキナミシャク(蛾)
モンキキナミシャクに似ていますが、本種は外横線が前翅の下側(止まっていると内側)でグニャリと曲がります。地色はたいてい黄土色~茶色味を帯びていて、色の薄い横脈点の周りが目玉模様みたいに見えます。

プライヤハマキ蛾)
体長7mm程度。夏型と越冬型があり、斑紋が大きく異なります。ときにナラコハマキと紛らわしいです。個体変異も強いです。

ヘリオビヒメハマキ蛾)
クロサンカクモンヒメハマキに似ていますが、本種は秋に出現します。

ホソバシャチホコ蛾)

マエシロモンキノカワガ(蛾)

ミヤマセセリ
落葉樹の疎林の地表近くをパトロールして回り、翅を開いて地面にとまり日光浴をします。

ムラサキトガリバ蛾)
ニッコウトガリバに似ています。前翅中央部が白っぽい個体も多いです。

モンキキナミシャク蛾)
ナカモンキナミシャクに似ていますが、本種は外横線が前翅の下側(止まっていると内側)で曲がりません。個体変異は激しい方です。

サラサリンガ(蛾)

やってみよう!