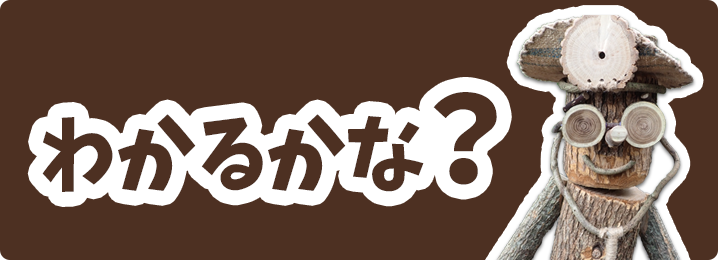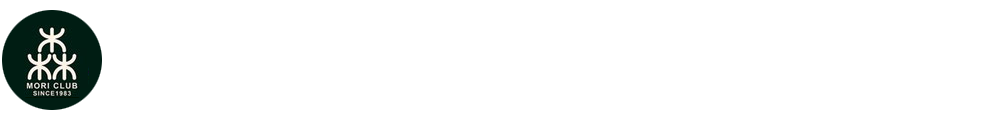6~7月
8月






つながってるいきもの
ハマダラハルカ
翅の黒い斑紋を散らしたなかなかおしゃれな中型のカです。学名には上品という意味のエレガンスが使われています。たいへん少ないうえ、春の短い間しかでてきませんのでなかなか見ることができません。カといえば水の中にいるボウフラを思い浮かべますが、ハナダラハルカの幼虫はネムノキの枯れ枝を食べます。ネムノキのまわりに落ちている枯れ枝にいます。春に見られ、壁や枯れ枝にポツンととまっていることが多いです。ハルカ科は日本にはこの1種です。世界にも3種しかいません。
ハマダラハルカ成虫

アオスジカミキリ
ネムノキの枯れ木や衰弱木などに集まり、また灯火にもよく飛来します。幼虫は餌となる枯れ木の樹皮下および材部を食べて成長し、1世代に2年かかります。6月頃に幼虫が成熟すると、材を食べ進んで出来たトンネル内の終点に蛹室を作り、出口の方向を向いて蛹化します。蛹室は石灰質みたいな物質で作られたドーム状の仕切りで区切られています。

ウスヅマクチバ(蛾)
成虫で越冬します。

カギバトモエ(蛾)

キタキチョウ
成虫は年に5・6回発生し、成虫で越冬もします。早春には越冬から目覚めて活発
に飛び回る姿が見
られます。山道の湿った地面で集団で吸水したりします。
キタキチョウの成虫

キタキチョウの幼虫

キタキチョウの卵

キタキチョウの蛹

キマダラカミキリ
外灯の灯りやクリの花によく飛来します。クヌギ・クリ・ネムノキなどの衰弱木の幹に集まります。赤褐色の下地に生える黄金色の微毛で覆われ、 光の加減で翅の模様の見え方がいろいろ変わります。

チャハマキ(蛾)
幼虫は、驚くほど多くの種類にわたる植物を食べます。

ナミスジコアオシャク(蛾)

ハグルマトモエ(蛾)
オスグロトモエのメスに似ていますが、前翅の「巴模様」が大きく、前翅の地色が淡くて全体にメリハリがあります。

フタテンオエダシャク(蛾)

ホタルカミキリ
ネムノキなど多くの広葉樹の伐採木に集まります。灯火にもきます。

ヨツキボシカミキリ成虫


やってみよう!