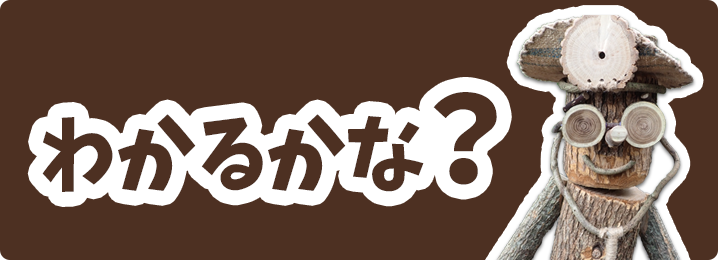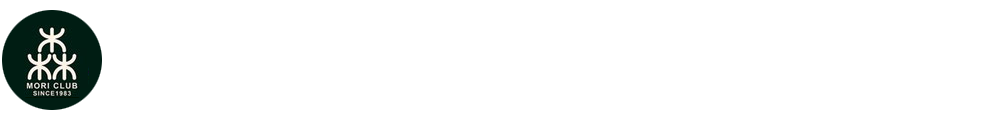2~3月
6月





紅梅(23.2.12 小城公園)

つながってるいきもの
ウメエダシャク
ウメの木を食べる有名な昆虫の一つはウメエダシャクというガです。幼虫はウメの葉を食べるシャクトリムシです。成虫は昼間ウメの木の周りをヒラヒラとゆっくり飛んで回っています。昔はそう多い昆虫ではなかったのですが、近年は庭に植えたウメなどでもよく見かけられるようになりました。よく似たガにトンボエダシャクがいますが模様が違います。
ウメエダシャク成虫



アカイラガ(蛾)
幼虫は大きな突起に、更に二次の刺を持っていますが、イラガ科の中で刺はかなり細い方です。
アカイラガの成虫

アカイラガの幼虫

ウスアトキハマキ(蛾)

ウスクリモンヒメハマキ(蛾)

ウスバツバメ(蛾)
繭は主葉脈の上に必ず作るようです。体の周りに糸を張って繭の基礎を作り、それに体液を染み込まして固めます。表面には凸凹の脆い殻が被り、これには外側の殻にのみ穴が開いており内側は硬い殻で守られています。
ウスバツバメの成虫

ウスバツバメの幼虫

ウスバツバメの繭

ウスバフユシャク(蛾)
ヤマウスバフユシャク、クロテンフユシャクに似ますが、本種は前翅外横線が緩やかなカーブを描きます。止まったとき左右のどちらが上になるかは、その都度変わるようで、決まってはいません。

ウチスズメ(蛾)

ウメスカシクロバ(蛾)

オオシモフリスズメ(蛾)
幼虫・蛹・成虫とも鳴きます(音を発します)。

オオバナミガタエダシャク(蛾)
春の個体は夏の個体より明らかに大型。前翅裏先端に特徴的な白い紋があります。ウスバミスジエダシャクに似てはいますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では一様に黒です。裏側の前翅先端部に淡白色の紋があります。前翅真ん中の2本の線が後翅に近づいても平行です。

オオミノガ(蛾)


オビカレハ(蛾)
オビカレハの成虫

オビカレハの幼虫

カレハガ(蛾)幼虫

キマエアオシャク(蛾)

クスサン蛾)

クロシタアオイラガ(蛾)

コスカシバ(蛾)

コフキサルハムシ
メリケン粉の中に落ちたのではないかと間違うほど、体に白い粉かいっぱいついています。手であまり触ると白い粉が取れて黒い地肌が出てきます。

イラガ(蛾)
幼虫は肉質突起上に多数の毒棘を持っており、接触時に毒液を注射し激痛を与えます。刺された部分は赤く腫れますが、3日位で治ります。カキの枝先などで見かけられる白っぽい繭は、非常に硬く、黒い帯状の模様はいろいろがありますが、全体的に褐色のものもあります。
イラガの成虫

イラガの幼虫

イラガの繭

サクラケンモン(蛾)の幼虫
黒線が濃くて環状、腎状紋が淡めに浮いています。

シロオビフユシャク(蛾

strong>スモモキリガ(蛾)
翅の縁に黒い点々が残ります。

チャミノガ(蛾)

ナミガタエダシャク(蛾)

ヒメシロモンドクガ(蛾)
幼虫は毒針毛はありませんが、強い接触により軽い赤味が出、1時間以内に治ります。
ヒメシロモンドクガの成虫

ヒメシロモンドクガの幼虫

ヒメヤママユ(蛾)
中齢幼虫と繭は先端の鋭い棘を持ち、接触すると痛みを感じ、軽い発赤や丘疹を生じます。短時間で治ります。
ヒメヤママユの成虫

ヒメヤママユの幼虫

ヒロヘリアオイラガ蛾)
主に市街地や果樹園などで見られる外来種です。幼虫は軽く触っただけで刺します。かなり痛いです。幼虫はアオイラガに似ていますが、本種幼虫は、背中中央に細く暗色の縦筋があり、2齢ぐらいまでは集団行動を取ります。
ヒロヘリアオイラガの成虫

ヒロヘリアオイラガの幼虫

マイマイガ(蛾)
幼虫の顔は(┃ω┃)。卵塊には産卵時にメスが植えた毛があります。
マイマイガの成虫

マイマイガの幼虫

モモスズメ(蛾)
クチバスズメに似ていますが、前翅の色、脚の色、触角の太さ(雌雄に注意)、大きさ、一番内側の横線の走り方などで区別できます。

モンシロドクガ(蛾)
幼虫は極めて多数の微細な毒針毛を持っていて、蕁麻疹のような皮膚炎を起こします。痒みはとても強く治癒に約10日かかります。
モンシロドクガの成虫

モンシロドクガの幼虫

ヤツメカミキリ
成虫はウメやサクラの幹に集まりますが、ウメノキゴケの色に似ていて、なかなか見つけにくいです。

ルリカミキリ
幼虫はこれらの生木の樹皮下を盛大に食べます。成虫はこれらの植物の葉にとまり、主脈を裏側から食べます。敏感ですぐに飛んで逃げますが近くにとまります。
ルリカミキリの成虫

ルリカミキリの食べ痕

やってみよう!