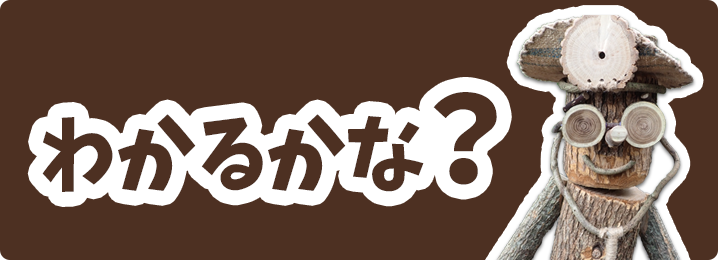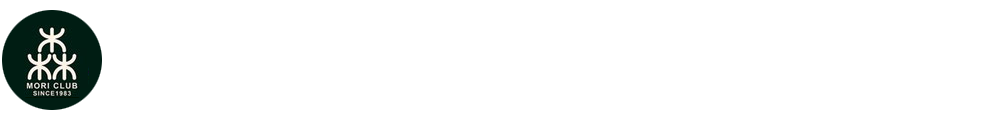5月
10月





シイの花 木全体がクリーム色の花におおわれてきれいです。(神埼市 日の隈公園)

つながってるいきもの
ベーツヒラタカミキリ
シイの巨木がある林があったら懐中電灯を持って夏の夜見回りに行きましょう。カが喜んでやってきますが目的はカではありません。大きなシイの枯れた低い部分を見て歩くと楕円型に穴が開いているのが目に付きます。よく見ると触角の先が出ていたりしますので、細い枯れ枝のさきなどで穴の中をつついてみましょう。ベーツヒラタカミキリが出てきます。
ベーツヒラタカミキリのオス

ベーツヒラタカミキリのメス

ベーツヒラタカミキリの脱出孔

外をうかがうベーツヒラタカミキリのオス

アトジロエダシャク(蛾)
春にだけ現れる蛾です。

ウコンカギバ(蛾)
ヒメウコンカギバに似ています。本種は翅頂<付近の紋が薄く、外横線も後翅付近で濃くならない傾向があるのですが、解剖しないと正確な区別は難しいです。
ウコンカギバ幼虫

ウコンカギバ成虫

ウコンカギバ蛹

ウスグロフトメイガ(蛾)
ナカアオフトメイガに似ていますが、本種の前翅外横線が後縁あたりで斜めに曲がる傾向があります。

ウスクモエダシャク(蛾)

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

カシコスカシバ(蛾)

カシワマイマイ(蛾)
カシワマイマイの成虫

カシワマイマイの幼虫

カタジロゴマフカミキリ
カシ・シイ類など多くの種類の枯木に集まり、灯火にも飛んできます。

シイシギゾウムシ
成虫はシイの実の中に産卵するためシイに集まるようですが、椎の木の樹高が高いため、なかなか本種を見ることはできません。

シロスジカミキリ
日本産では横綱級の大きなカミキリムシです。捕まえると胸の部分を伸縮させてギーギーと鳴きます。昼間はアカガシやアラカシの梢にいて枝や皮をかじって食べていますが、夜になると幹まで降りてきて樹皮を噛んで傷つけ、そこに産卵します。一個産んだら少し横に動いてまた産卵を繰り返しますので、幹を横に取り巻いたような産卵痕が残ります。
シロスジカミキリ成虫

シロスジカミキリ産卵痕

シロスジカミキリ幼虫の食害

シロスジカミキリ幼虫の食痕

ヒメウコンカギバ(蛾)
ヒメウコンカギバの成虫

ヒメウコンカギバの幼虫

フタオビミドリトラカミキリ
マテバシイをはじめ各種の広葉樹の伐採木に集まるほか、各種の花にもきます。沿海性のカミキリです。

ベーツヤサカミキリ
成虫はシイ・クリなどの花にあつまるほか、灯火にも飛来します。

マエシロモンキノカワガ(蛾)

ルリシジミ
各種の花に来るほか、オスは路上で吸水します。近年は北上種のヤクルリシジミのほうがよく見かけられます。
ルリシジミの成虫


ルリシジミの卵

ルリシジミの幼虫


キクスイモドキカミキリ
カシ・シイ類など多くの種類の枯木に集まり、灯火にも飛んできます。

カシルリオトシブミ
いるいろな植物で見られますが、イタドリの葉にいることが多いです。

やってみよう!