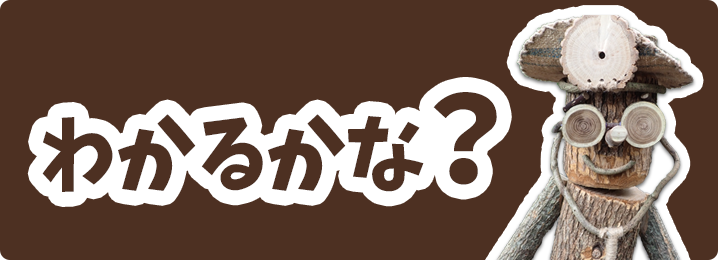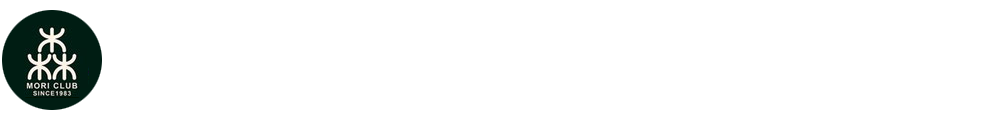9月
10~11月





樹皮はところどころはげ落ちパズル模様になる

秋には葉は黄色く色づく

つながってるいきもの
ニレハムシ
ニレハムシは幼虫、成虫ともにアキニレやケヤキの葉をボロボロにたべてしまいます。薄茶色の薄い翅を持った小さなコウチュウで、主に葉の裏に見られます。年に2度ほど発生し、幼虫は薄黄色の地に黒い小さな斑点がたくさんあり、芋虫型です。幼虫は地中などで蛹になります。秋に出た2回目の成虫は木の皮の間や、落ち葉の中などで成虫越冬します。
ニレハムシ成虫

ニレハムシ成虫と食痕

ニレハムシ食痕

アトジロエダシャク(蛾)
春にだけ現れる蛾です。

ウンモンスズメ(蛾)

キリバエダシャク(蛾)

クロツヤミノガ(蛾)

シロシタケンモン(蛾

シロシタヨトウ(蛾)

シロスジカミキリ
日本産では横綱級の大きなカミキリムシです。捕まえると胸の部分を伸縮させてギーギーと鳴きます。昼間はアカガシやアラカシの梢にいて枝や皮をかじって食べていますが、夜になると幹まで降りてきて樹皮を噛んで傷つけ、そこに産卵します。一個産んだら少し横に動いてまた産卵を繰り返しますので、幹を横に取り巻いたような産卵痕が残ります。
シロスジカミキリ成虫

シロスジカミキリ産卵痕

シロスジカミキリ幼虫の食害

シロスジカミキリ幼虫の食痕

ムクツマキシャチホコ
9月頃、ムクノキの枝先を丸坊主にする幼虫の集団がいます。樹の下には大量の糞が落ちていますので上を見上げなくてもいるのがわかります。にっくき毛虫ですが、よく見るとなかなか素敵な色合いをしていますね。この成虫は枯れ枝の切れ端をまねているとしかおもえないおもしろい格好をしています。枯れ枝の写真を出しますので比べてみてください。
ムクツマキシャチホコ

枯れ枝

ムクツマキシャチホコの交尾

ムクツマキシャチホコ幼虫

ムクツマキシャチホコ幼虫ようちゅう

ムクツマキシャチホコ幼虫

マメドクガ(蛾)
マメドクガの成虫

マメドクガの幼虫

シラホシキクスイカミキリ
カバノキ類・ブナのなどの伐採木に見られます。シラホシカミキリやニセシラホシカミキリによく似ています。

ウスキツバメエダシャク(蛾)

ウスバミスジエダシャク(蛾)
前後の翅の横脈紋が4つの細長い目のように見えます。オオバナミガタエダシャクに似ていますが、横脈紋の状態、特に後翅の横脈紋が本種では楕円形の紋の中に細長い線状の淡色部があります。裏側の前翅先端部に淡白色の紋がありません。

オカモトトゲエダシャク(蛾)
クワトゲエダシャクに似ていますが、本種は中横線(黒い線)の外側に広く白い帯が出ます。メスはなかなか見つかりません。幼虫は触るとすぐに丸くなります。色的には鳥のフンにでも擬態しているようですが、いつも歩き回っているので、かえって目立ってしまっているようです。1~2週間で蛹化しますが、羽化するのは来春です。夏、冬越しが難しく、普通種の割には飼育羽化させるのが難しいガです。

ゴマフキエダシャク蛾

シャチホコガ(蛾)
シャチホコガの成虫

シャチホコガの幼虫

トビモンオオエダシャク蛾
トビモンオオエダシャクの成虫

トビモンオオエダシャクの幼虫

ニトベエダシャク(蛾)

ヒメノコメエダシャク蛾
体を斜めにして、腹部の先端を片方の翅に触るように曲げてとまることが多いです。

ヒメヤママユ(蛾)
中齢幼虫と繭は先端の鋭い棘を持ち、接触すると痛みを感じ、軽い発赤や丘疹を生じます。短時間で治ります。
ヒメヤママユの成虫

ヒメヤママユの幼虫

モンシロツマキリエダシャク蛾
平野まで広く分布するので見かけることが多いです。

リンゴツノエダシャク蛾

やってみよう!