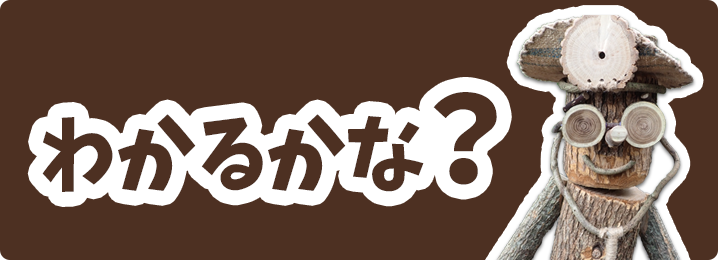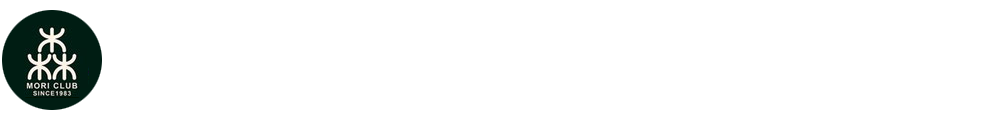4月
10月





つながってるいきもの
マツノマダラカミキリ
外国から輸入された材木について日本へ入ってきたマツノザイセンチュウが、もとからいたマツを食べるマツノマダラカミキリの生態に乗っかってマツの木の中に入り込み、次々に松林を枯らしています。アカマツもクロマツも松枯れ病にかかり、海岸の美しかった松林などで多くのマツが枯れてしまうなど、被害は全国に広がって大変なことになっています。
枯れ始めたアカマツ

枝をかじるマツノマダラカミキリ

樹皮下に見られる幼虫の食痕

切り倒された被害木

マツカレハ
松の葉を食べるので幼虫はマツケムシと呼ばれています。触るとトゲの束で刺してきます。トゲの先には毒があり、刺されるととても痛みます。この毒棘は繭を作るときに内側から外に向けて突き刺しており、繭に触るだけで刺されます。秋に幹にむしろなどを巻いておくと、マツケムシが冬越しのためにそのなかに入り込み、外して焼くと毛虫駆除ができます。
マツカレハ成虫

マツカレハ成虫

マツカレハ繭

マツカレハ幼虫

マツカレハ幼虫

孤巻

孤巻

孤巻で捕獲されたマツカレハ幼虫

孤巻で捕獲されたマツカレハ幼虫

ウバタマコメツキ
冬場にマツの朽ち木を崩すと中で見つかります。

枯れたマツを食べる昆虫
クロマツに限らずアカマツもですが、マツクイムシにやられて枯れたマツをよくみます。これらの枯れマツにはその後利用する昆虫がいて、幼虫が枯れた材の部分を食べます。なるべく皮のまだついている枯れ木を選んで、冬から春にかけて枯れたマツの木の皮を剥がしてみるとすでに成虫になっているもの、まだ幼虫のものなどいろいろな昆虫を発見できます。
ウバタマムシ


オオゾウムシ

クロカミキリ

クロタマムシ

マツアナアキゾウムシ幼虫

オオゾウムシ
マツなどの腐朽木にいます。倒木上を歩行したり、雑木林の広葉樹の樹液に来ますが、夜には灯火にも飛来します。手で触れると脚を縮めて死んだふりをします。

カタジロゴマフカミキリ
カシ・シイ類など多くの種類の枯木に集まり、灯火にも飛んできます。

クロカミキリ
灯火に集まる習性があり、マツ・スギ・ヒノキなど針葉樹の倒木などでよく見らます。

クロスズメ蛾

クロタマムシ
マツ類・モミ類などの衰弱した枝や針葉樹の枯れ木で見られ、幼虫はその材を食べて育ちます。

サビカミキリ
夜間食樹に集まってきます。灯火にも飛来します。

ツガカレハ(蛾)
幼虫は多数の短刺毛を持っており、触ってしまうと痛みや痒みははげしくなり、腫れと小さなプツプツが見られます。治癒に5~10日かかります。

ツマオビアツバ(蛾)

ナカウスエダシャク(蛾)
ウスバキエダシャク、ウスバシロエダシャク、およびヒメナカウスエダシャクに似ていますが、本種は春~晩秋に出現し低地~山地にいます。前翅は全体に暗く、中央部分がメスでは白。地味なエダシャクの中で晩秋まで残っているのはこの種がほとんどです。


フタヤマエダシャク(蛾)

ホンドニセハイイロハナカミキリ
マツ類の立ち枯れや伐採木に日中集まります。

マツアトキハマキ(蛾)

ムツボシタマムシ
幼虫はマツの枯木を食べ、成虫は枯れたマツに集まります。よく似た種が複数います。

ムネアカクロハナカミキリ
平地から山地に見みられ、ガマズミ・リョウブなどの花にきます。よく似たクロハナカミキリは本州の高標高地から北海道に産します。

やってみよう!