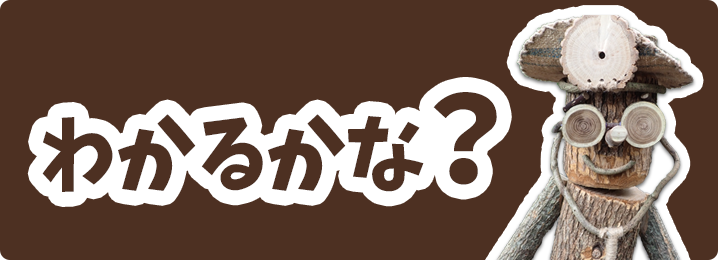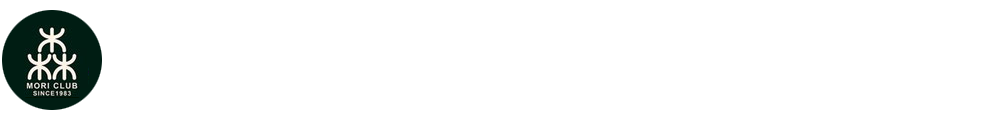4月
10月





ケヤキの木材の木目は美しいので家の大黒柱に使われてます。

太鼓の胴の部分にも使われてます。

つながってるいきもの
ヒロヘリアオイラガ
ケヤキが、街中の道路に沿って植えられたりしていますね。これらのケヤキの幹をよく見ると、不思議なものがついています。楕円型した卵を幹に押し付けたような形をし、その多くの上部が丸く切り取られて大きな穴が開ひらいています。ヒロヘリアオイラガという外来のガが羽化したあとの繭です。幼虫は棘だらけの格好をして、触れると刺します。痛いです。
ヒロヘリアオイラガ成虫

ヒロヘリアオイラガの羽化後のまゆ


ヒロヘリアオイラガの幼虫

ニレハムシ
ニレハムシは幼虫成虫ともにアキニレやケヤキの葉をボロボロにたべてしまいます。薄茶色の薄い翅を持った小さなコウチュウで、主に葉の裏に見られます。年に2度ほど発生し、幼虫は薄黄色の地に黒い小さな斑点がたくさんあり、芋虫型です。幼虫は地中などで蛹になります。秋に出た2回目の成虫は木の皮の間や、落ち葉の中などで成虫越冬します。
ニレハムシ食痕

ニレハムシ成虫

ニレハムシ成虫と食痕

マエキオエダシャク
日本では本州~南西諸島まで広く分布し、成虫は4月と6月~8月の年間2回出現します。一様に灰褐色の翅をもつやや小型のガで、翅を真横に広げてとまり、灯火にもよく飛んできます。幼虫はシャクトリムシですが、体の前半が膨らんでいて、色々と色彩変異に富んでいます。主にモチノキ科のイヌツゲ、アオハダ、クロガネモチ、ケヤキなどを食べます。
マエキオエダシャク幼虫

マエキオエダシャク成虫

ヤマトタマムシ
玉虫厨子に一面埋め込まれているのはこのヤマトタマムシの翅です。金緑色に赤い筋が入るその翅はため息が出るほど美しいです。昔はこのたま虫の死骸をタンスに入れておくと着物が増えるという言い伝えがあったそうです。幼虫はエノキ、ケヤキなどの枯れた部分を食べ、成虫はよくエノキやケヤキの枝先で翅をきらめかせて飛び回ったりします。
ヤマトタマムシ成虫

ヤマトタマムシの脱出孔

アカタテハ(蝶)
山から人里までの広い環境で見られ、花や樹液にあつまるほか、岩や地面に翅を開いてよくとまっています。多くは成虫で越冬します。よく似た種にヒメアカタテハがいますが、後翅の模様がかなり違います。

ウスタビガ(蛾)
幼虫は触ると鳴きます。
ウスタビガの成虫


ウスタビガの幼虫


ウスタビガの繭

ウスバフユシャク(蛾)
ヤマウスバフユシャク、クロテンフユシャクに似ますが、本種は前翅外横線が緩やかなカーブを描きます。止まったとき左右のどちらが上になるかは、その都度変わるようで、決まってはいません。

ウンモンスズメ(蛾)

エルモンドクガ(蛾)

オオアカオビマダラメイガ(蛾)

カシルリオトシブミ
いろいろな植物で見られますが、イタドリの葉にいることが多いです。

キスジトラカミキリ
広葉樹の伐採木や花に来ます。

キドクガ(蛾)
キドクガの成虫

キドクガの成虫

クスサン蛾)

クロテンフユシャク(蛾

シロオビフユシャク(蛾

シロシタケンモン(蛾

シロスジカミキリ
日本産では横綱級の大きなカミキリムシです。捕まえると胸の部分を伸縮させてギーギーと鳴きます。昼間はアカガシやアラカシの梢にいて枝や皮をかじって食べていますが、夜になると幹まで降りてきて樹皮を噛んで傷つけ、そこに産卵します。一個産んだら少し横に動いてまた産卵を繰り返しますので、幹を横に取り巻いたような産卵痕が残ります。
シロスジカミキリ成虫

シロスジカミキリ産卵痕

シロスジカミキリ幼虫の食害

シロスジカミキリ幼虫の食痕

スジモンヒトリ(蛾)
スジモンヒトリの成虫

スジモンヒトリの幼虫

スジモンヒトリの繭

トビイロカミキリ
クリなどの花に集まり、灯火にも来ます

ナシイラガ(蛾)

ナミガタチビタマムシ
冬場に主にムクノキの樹皮をはがすと集団で成虫越冬しているのが見つかります。ヤノナミガタチビタマムシにそっくりです。

ニレキリガ(蛾)

ヒオドシチョウ
年1化。成虫で越冬。樹液に集まります。
ヒオドシチョウの成虫

ヒオドシチョウの幼虫

ヒオドシチョウの蛹

ヒシモンナガタマムシ
エノキの伐採木に集まったり、ケヤキの樹皮下で成虫越冬するのを見たりします。

ヒメクロイラガ(蛾)
幼虫は肉質突起上に多数の毒棘を持ち、接触時に激痛を与
えます。発赤や丘疹
を生じますがほとんど痒みはなく、3日くらいで治ります。
ヒメクロイラガの幼虫

ヒメクロイラガの被害を受けた葉

ヒロバトガリエダシャク(蛾)
春のエダシャクの定番です。ホソバトガリエダシャクに似ていますが、本種の前翅が太く、翅が白っぽいです。また、後翅は純白です。

プライヤエグリシャチホコ(蛾)

ホソウスバフユシャク(蛾)
Inurois属では冬の最後の方に出現する種。冬の終わりを告げる蛾です。

マイマイガ(蛾)
幼虫の顔は(┃ω┃)。卵塊には産卵時にメスが植えた毛があります。
マイマイガの成虫

マイマイガの幼虫

ミドリハガタヨトウ(蛾)

ヤノナミガタチビタマムシ
冬場に主にケヤキの樹皮をはがすと集団で成虫越冬しているのが見つかります。ナミガタチビタマムシにそっくりです。

ユミモンシャチホコ
シャチホコガ科の何種かの成虫は、植物に化けて鳥などから食べられないように知恵を絞っています。中でもかなりよく化けているのがこのユミモンシャチホコです。古い枯れ枝が落ちてきたときに枝の一部が短く折れ落ちた格好をしています。折れ口にはなんと年輪までありますよ。危険を感じると丸まって足を引っ込め、突くとコロコロ転がります。
枯れ枝をまねするユミモンシャチホコ

年輪までまねるユミモンシャチホコ

ふつうにとまったユミモンシャチホコ

やってみよう!